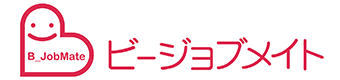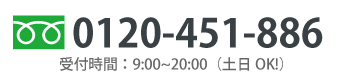愛知県岡崎市に伝わる民謡「岡崎五万石」とは
2025.11.13
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。
地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『愛知県岡崎市に伝わる民謡「岡崎五万石」とは』ということでお伝えしていきたいと思います。
日本の民謡には、その土地の歴史や人々の暮らし、そして文化が色濃く反映されています。愛知県岡崎市にも、そんな地域に根ざした民謡として、古くから親しまれてきた「岡崎五万石」があります。
ここでは、民謡「岡崎五万石」の歴史的な背景、歌詞に込められた意味、そして現代に受け継がれる役割について、深く掘り下げていきます。
■民謡「岡崎五万石」の歴史と由来
□岡崎五万石の歴史
民謡「岡崎五万石」は、単なる地域の民謡ではなく、お酒の席で歌われる「お座敷唄」として知られており、その歴史は独特な広がりを見せています。この歌のタイトルは、徳川家康の生誕地として知られる岡崎藩の石高、五万石に由来しています。
領地としては決して大きくありませんでしたが、岡崎の人々は家康の出身地であることに大きな誇りを持っていました。
□岡崎五万石の由来
この歌の源流は、東海地方から関東にかけて広く歌われていた「ヨイコノ木遣り」という仕事歌にあると言われています。それが江戸の鳶職人の間で人気となり、やがて花柳界にも広まってお座敷歌として歌われるようになりました。
地元岡崎では、一時期歌われなくなったこともありましたが、大正時代に復活。そして、昭和2年(1927年)には、詩人・野口雨情と作曲家・中山晋平が手掛けた新しい「新五万石(岡崎城下小唄)」が誕生し、古くからの「岡崎五万石」も、改めて歌詞を整え、格調高いお座敷歌として歌い継がれるようになったそうです。このように、この歌は仕事歌からお座敷歌へと姿を変えながら、岡崎の歴史と共に歩んできました。
■歌詞と特徴
民謡「岡崎五万石」の歌詞には、岡崎の誇りと、当時の人々の暮らし、そして豊かな自然が凝縮されています。この歌を聴く際、歌詞に耳を傾けてみると、岡崎の魅力がより深く感じられるでしょう。
□岡崎五万石の歌詞
五万石でも岡崎様は アーヨイコノシャンセ
お城下まで船が着く ションガイナ
アーヤレコノ 船が着く
お城下まで船が着く ションガイナ
アーヨーイヨーイ ヨイコノシャンセ
まだまだ囃そ
□歌詞に込められた岡崎の誇り
「五万石でも 岡崎様は お城下まで 船が着く」という歌詞は、岡崎の人々が抱いていた大きな誇りを表しています。当時の岡崎城下町では、城からわずか3〜4分の場所に船を着けられる場所があり、これは地元の人々にとって大きな自慢でした。
この短いフレーズには、石高は小さくとも、徳川家康の生誕地であり、交通の要衝でもあった岡崎の繁栄と人々の自信が込められていると言われています。
□岡崎五万石の特徴
この歌の特徴は、単なる歌詞の情景描写だけではありません。歌の間に挟まれる「アーヨイコノシャンセ」や「ションガイナ」といったお囃子詞は、歌い手自身がすべて歌う形式になっています。これらの詞は、この歌が木遣り歌を源流としていることを示しています。
また、この歌と三味線の伴奏は、不即不離の関係で、完全に一致するのではなく、微妙にずれていくのが特徴です。このずれが、お座敷歌としての上品な雰囲気と、歌に深みを与えています。
■まとめ
民謡「岡崎五万石」は、単なる地域の歌ではなく、岡崎の歴史と人々の誇りを伝える貴重な文化遺産とも言えます。
仕事歌を源流にお座敷歌として発展したこの歌は、歌詞に当時の繁栄や人々の自慢を織り込み、軽快なリズムと独特な音楽的特徴で人々を魅了してきました。
現代においても、時代を超えて岡崎のアイデンティティを歌い続けています。この歌の背景と意味を知ることで、岡崎の文化をより深く味わうことができるでしょう。
今回は『愛知県岡崎市に伝わる民謡「岡崎五万石」とは』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
「BSG株式会社」お仕事情報サイト
ビージョブメイト
お電話でご相談をされたい方はコチラからどうぞ!(土日も歓迎、AM9:00~PM20:00)
フリーダイヤル0120-451-886